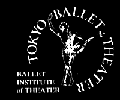沿革・理念
|
|
東京バレエ劇場バレエ団の
|
||||
| 東京バレエ劇場バレエ団がいつ結成されたかという事については、実は判断の難しいところなのです。対外的には昭和43年(1968)と申し上げておりますが、主宰者の榎本(川島)誠之介が「東京バレエ劇場」の名称を使いはじめたのは昭和30年代(1955年以降)前半からでした。 東京バレエ劇場は主宰者の榎本誠バレエ学園<昭和27年:1952設立>の発展形態として、バレエ学校部門と本格的なバレエ公演を企画・実施するプロデュース部門を兼ね備えた組織として誕生しました。従って東京バレエ劇場の主催する有料公演は、すなわち東京バレエ劇場バレエ団公演と呼んでもほぼ差し支えない訳ですし、榎本誠バレエ学園時代にも選抜在校生による「榎本バレエ団」名義のあるいは「榎本バレエ・グループ」名での本格的バレエ公演は行われておりました。 ですから現在の東京バレエ劇場バレエ団のルーツは第一回の榎本バレエ・グループ公演<昭和30年:1955>にあると申し上げた方が正確かもしれません。 |
|||||
 榎本バレエ・グループ公演:1955 |
榎本バレエ団、あるいは榎本バレエ・グループ名義での活動は、本邦初演の「奇妙な店」「こわれがめ」「夢のかけら」等画期的作品を世に送り出すなど多くの業績を残しましたが、東京バレエ劇場設立以降の公演活動はより活発化します。 当時の代表作としてはオペラ“蝶々夫人”のグランド・バレエ化作品「長崎物語」を筆頭に挙げる事ができるでしょう。この作品は榎本が5年の歳月をかけて構想を練り上げた3幕5場の大作バレエ です。<昭和39年:1964初演> そして我が国バレエ界に多大な足跡を残した東京バレエ学校の設立とその解散劇にまつわる現在のチャイコフスキー記念東京バレエ団との合体時代を経て(この間は「新東京バレエ学校」の名称が使われました。詳しくは東京バレエ劇場附属バレエ学校沿革のページをご覧下さい)、現在にその名を継ぐ東京バレエ劇場バレエ団の基礎が固まったのが昭和43年(1968)の事でした。 |
||||
| 新東京バレエ学校時代の昭和42年(1967)に主任教師として着任した、元ニューヨーク・シティ・バレエ団のプリンシパルにしてジョージ・バランチンの片腕と称されたロイ・トバイアス氏は、引き続き元の名前に戻った東京バレエ劇場附属バレエ学校の主任教授を昭和46年(1971)まで続けます。トバイアス氏という頭脳を得てバレエ学校の選抜メンバーで結成された東京バレエ劇場バレエ団は、その後トバイアス氏振付作品を中心に五年間に10回の公演を行います。 演目には「くるみ割り人形」「白鳥の湖」「ライモンダ」「レ・シルフィード」などの古典作品を始め、バランチン直伝の「弦楽セレナーデ」「うぐいす」「OCTET」「アゴン」「アポロン」「白雪姫」「子どもの遊び」「放蕩息子」など西洋に想をもとめた創作作品から「邦楽器による六重奏曲」「西寺」「さむらい」など我が国伝統を大胆に取り入れた創作作品など幅広いものでした。<過去の作品は「過去の名作集」のページでご覧頂けます> |
 「長崎物語」1964年 |
||||
 「うぐいす」1971年公演 |
ダンサーとしては東京バレエ劇場のメンバー以外からも、現在我が国バレエ界の中枢を担っておられる尾本安代女史、大原永子女史、小川亜矢子女史、江川明氏(故人)、高田止戈氏、漆原宏樹氏、横瀬三郎氏、野呂修平氏、高木俊徳氏、榎本晴夫氏、西優一氏、桑原君昂氏などの客演を仰ぎ、当時のバレエ団員には現在我が国を代表する女優となられた松坂慶子さんがおられました。 さてトバイアス氏の後を受けて東京バレエ劇場附属バレエ学校の主任教師に着任したのはロンドン・フェスティバル・バレエ団の芸術監督であったジャック・カーター氏<故人>です。 カーター氏は既に英国を代表する振付家として確固たる名声を築かれておられましたが、昭和46年(1971)から49年(1974)にかけ、東京バレエ劇場バレエ団の為に多くの作品を振付けます。 |
||||
| と同時に、カーター氏は海外から優れたダンサーを東京バレエ劇場バレエ団公演の為に招聘しました。 昭和46年(1971)の「コッペリア」公演の為に英国ロイヤル・バレエ団等で活躍していたキャロル・グラントとパリ・オペラ座バレエ団等で活躍していたロバート・ベストンソーが、翌47年にはカーター氏の傑作創作の呼び声高い「ザ・ウイッチ・ボーイ」上演の為にロンドン・フェスティバル・バレエ、ABT等で活躍していたジェラード・シヴィリトゥが、翌48年の「コッペリア」公演では再びキャロル・グラントとロバート・ベストンソーが東京バレエ劇場バレエ団の舞台を飾りました。 |
 「ザ・ウイッチ・ボーイ」1972年 大原永子、小川亜矢子、ジェラード・シヴィリトゥ客演 |
||||
| カーター氏による「コッペリア」と「ジゼル」は、トバイアス氏による「くるみ割り人形」と並んで現在でも東京バレエ劇場バレエ団を代表する重要なレパートリーとなっています。 | |||||
 キャロル・グラント |
昭和50年代(1975年以降)に入ると、東京バレエ劇場バレエ団の公演は、ほぼ現在の夏と春の定期公演というスタイルが確立します。 昭和55年夏公演(1980)では「人魚姫」を初演、翌56年冬の「くるみ割り人形」公演にはロンドン・フェスティバル・バレエ団プリマのパトリシア・ルアーネと英国ロイヤル・バレエ団プリンシパルのアラン・ドゥブリューをゲスト招聘、続く57年冬の「コッペリア」と「くるみ割り人形」の抜粋公演にはロンドン・フェスティバル・バレエ団のプリマとプリンシパルであるルチア・トゥルーリアとマッツ・スコーグが客演、昭和59年冬の「眠れる森の美女」と 60年冬の「白鳥の湖」にはヴアルナ国際バレエ・コンクール銅メダリストのマーメット・バルカン<後者にはロンドン・フェスティバル・バレエからヴィヴィアン・ローバーも招聘>が客演するなど東京バレエ劇場バレエ団公演の舞台は、常に世界のトップ・クラスのダンサーによって飾られました。 |
||||
| 平成年代(1989年以降)に入ると、東京バレエ劇場はトバイアス氏、カーター氏といった英米系のバレエのみならず、ロシア・バレエにも急速に接近します。その陰にはロシア屈指の日本通にしてロシア・バレエ界にも精通している現代絵画画廊主宰者にして美術評論家、ニコライ・トカチェンコ氏と榎本の出会いがありました。ニコライ氏と意気投合した榎本は、ニコライ川島バレエ・アート・インターナショナル(NKBAI)を設立し,現代ロシア・バレエの最上の血を東京バレエ劇場バレエ団に注入すると同時に、現代ロシア・バレエの粋を積極的に我が国に紹介し始めました。(「近年の主な海外ダンサー・バレエ団招聘企画公演」のページをご参照下さい) |
|||||
 エレーナ・クニャジコーワ |
以後、東京バレエ劇場バレエ団の舞台を、世界でたった三人しかいないヴァルナ、モスクワの両国際バレエ・コンクールのダブル金メダリストにして現代ロシアの生んだ巨匠、ユーリ・グリゴローヴィチの愛弟子と言われたエレーナ・クニャシコーワを筆頭に、マリィンスキー記念キーロフ・バレエ団プリマ、ユリヤ・マハリナ、ボリショイ・バレエ団の代表的ソリスト、ウラジーミル・ネポロージニィーなど現代ロシア最高のダンサーが頻繁に飾ります。 (詳しくは東京バレエ劇場バレエ団「近年の主な公演活動」のページをご覧下さい) 現在の東京バレエ劇場バレエ団は、ロシア国立ノボシビリスク・バレエ団との交流を深め、両団メンバーによる国際交流コンサートなどが定期的に開催され、同団芸術監督セルゲイ・クルプコ氏による指導も仰いでいます。と、同時に故ジャック・カーター氏の著作権継承者であるジェラード・シヴィリトゥ氏による作品上演なども積極的に行っています。 |
||||
| 東京バレエ劇場バレエ団は、常にその視野の中に“世界”を置いて、今も前進し続けております。 (現団員は「バレエ団員・教師フォト・アルバム」のページでご覧下さい) | |||||